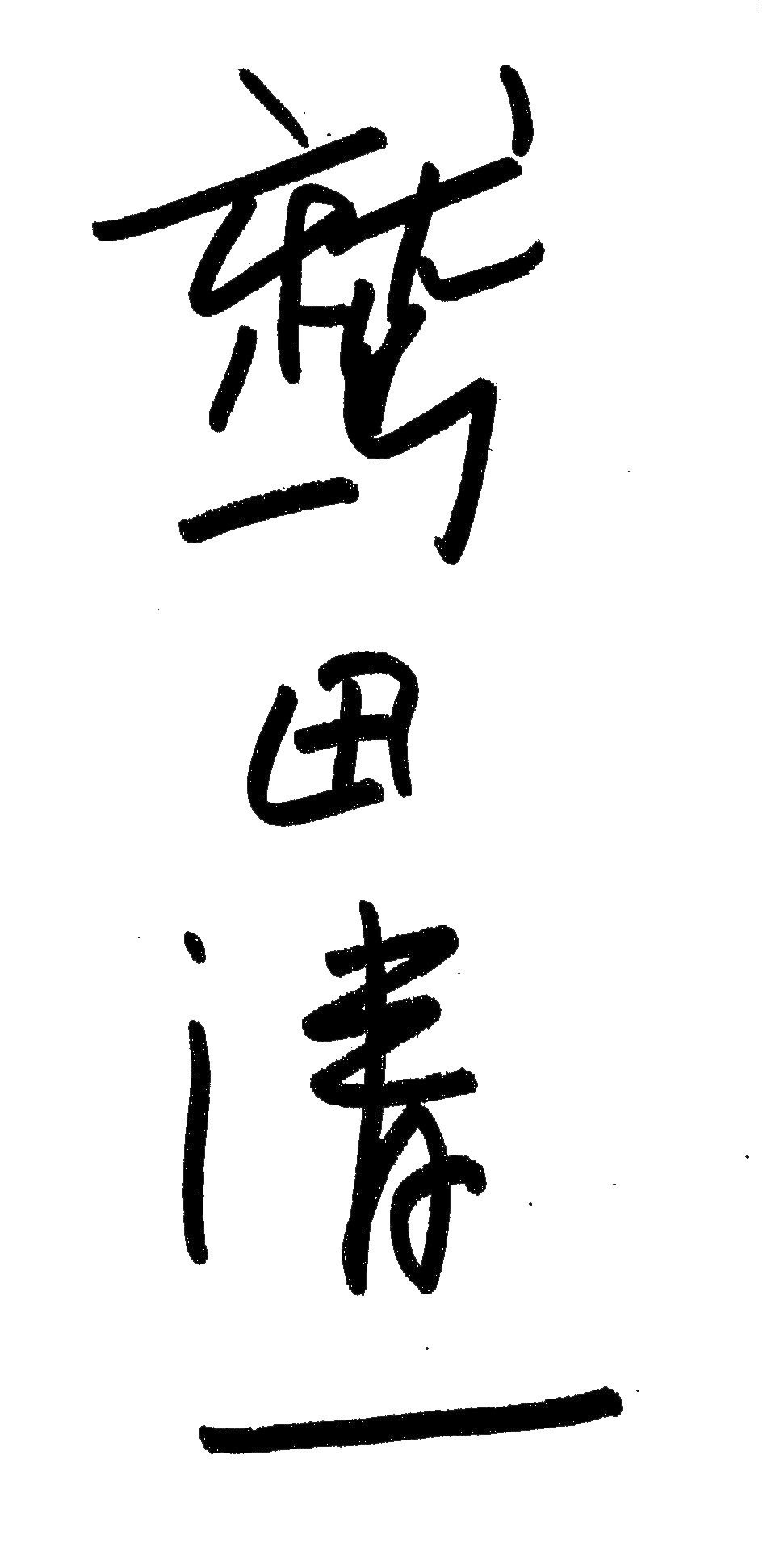時代のこの蠕動をあのひとならどう受けとめるだろうかと、折にふれて問うてみたくなる、そんな書き手がたぶんだれにもいる。わたしにとって「吉本隆明」がそのひとだった。そしてその謦咳には、マスメディアでない小さな出版物のなかで、かならずふれることができた。以後、どんな問いにも、それが庶民の日々の細々とした疼きの理由であっても、「わたしはこんなふうに考える」といつも答える用意があるというのが〈思想家〉の条件であると、わたしは考えるようになった。
吉本隆明は、二階ではなく一階で、台所の音を聴きながら、ぐずる子をあやしながら、家の前を行き来する人びとの気配に耳を澄ましながら、仕事をするような人だった。そういう〈歴史〉の地べたから、しかも〈歴史〉をじぶんという存在の根拠となるはずのものに繋いで、そしてそこからしか声を立ち上げない人だったから、多くの仕事は「二十五時」以降になされた。思想というものは、暮らしのなかにこの「二十五時」をどう押し込むかにかかっていることを、教えてくれたひとだった。